- コンプライアンス
反社チェックツール・サービスで企業のコンプライアンスを守ろう
公開日:
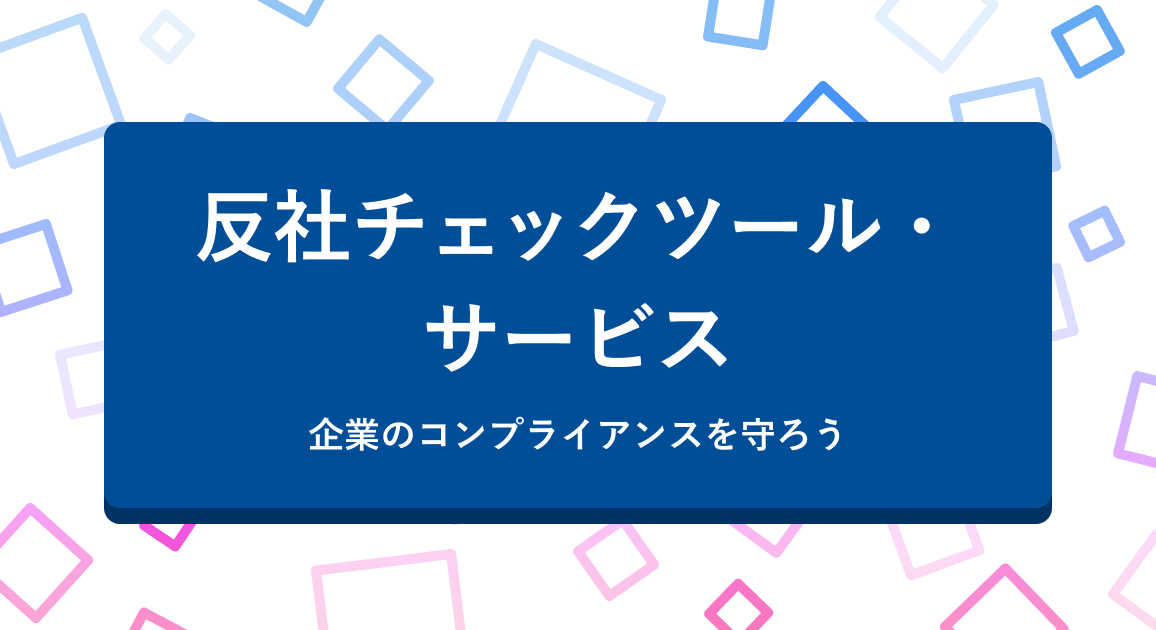
企業は、反社(反社会的勢力)と知らないうちに関わりを持ち、暴力団の資金源となる取引をしたり、不当な要求による被害を受けたりすることは、コンプライアンスの観点や企業防衛の観点からも避けなければなりません。普段から反社への対応策を講じておくとともに、取引先など関係者の反社チェックを実施しておくことが、リスク回避へとつながります。本記事では、反社に関する簡単な基礎知識と合わせて、代表的な反社チェックツールを紹介します。
※本記事は2020年4月に作成されました。掲載されている内容は作成時点の情報です。
目次
企業が反社をチェックする目的
内閣総理大臣が主宰する「犯罪対策閣僚会議」によれば、暴力団をはじめとする反社は、本来の姿を隠した上で企業としての活動や政治的または社会的活動を行っています。また、証券取引や不動産取引などの経済活動を通じて、資金源の確保が行われていることもあるといいます。
こうした現状から、企業はコンプライアンスの観点や不当な被害に対する防衛手段として「反社チェック」を行う必要があります。
政府、関係官庁、各自治体が定める反社排除の法令・ガイドライン
反社を排除していくことは、一般市民や企業活動の安全を守り、正常な社会生活を維持するためにも欠かせません。公的機関が定める法規定やガイドラインには、主に次のようなものがあります。
・「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議)
「世界一安全な国、日本」の復活を目指して発足した犯罪対策閣僚会議が、2007年に示した指針。内閣総理大臣が主宰し、全閣僚が構成員となっています。
・「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」(金融庁)
2013年12月に金融庁が示した報道発表資料。金融庁と各金融機関・業界団体が、反社(反社会的勢力)との関係遮断を確実に行うための取り組みを具体的に示しています。
・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴対法)
暴力団が暴行や脅迫などの方法で、一般市民や企業に圧力を加えるような行為を取り締まる法律です。1992年に施行され、これまでは取り締まりが難しかった民事介入暴力への対策が盛り込まれました。
・「暴力団排除条例」(暴排条例)
各地方公共団体が、暴力団の資金源を断つことを目的に定めた条例です。名称は一部異なりますが、47都道府県および一部の市区町村で同様の条例が施行されています。
経団連が「経団連企業行動憲章」で定める反社排除の表明
東証一部上場企業を中心に組織する一般社団法人日本経済団体連合会(略称:経団連)は、「経団連企業行動憲章 実行の手引き」の中で、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決する」として、次のように表明しています。
1. 多様化する反社会的勢力、団体
近年、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動にも障害となる反社会的勢力、団体の活動は、以前に比べてますます知能化、巧妙化しつつあり、その多様化が進んでいます。暴力団活動もその例外ではなく、広域化、寡占化を進めると共に、その活動も多様化、悪質化の傾向を辿っています。
2. 暴力団対策法の施行と暴力団活動の変質
こうした動きに対応して、92年に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴力団対策法)を一つの契機に、市民や企業の間では反社会的勢力、団体に対する排除意識が確実に深まりつつあります。
しかし一方で、暴力団対策法の施行やバブル経済の崩壊等によって収入源が乏しくなったそれらの勢力は、恐喝、強要、嫌がらせなど企業を標的とした行動が目立つようになりました。またその手口も、あたかも合法的経済取引に見せかけるなど、益々、悪質、多様化しつつあります。
例えば、株主権の行使に名を借りて企業に揺さぶりをかけたり、社会運動や政治運動を仮装・標榜して企業に対して賛助金や協力費等の名目で金品を要求するケースも増えています。
3. 求められる反社会的勢力、団体との対決姿勢
こうした中で各企業は、社会的責任を強く認識して、その姿勢を正し、反社会的勢力、団体に屈服したり、癒着したりすることは厳しく戒め、かつ、これらの勢力や団体とは断固として対決する基本方針を改めて確立することが求められています。
最近、我が国を代表する大手企業においていわゆる総会屋への利益供与事件等の不正取引が次々と発覚するところとなり、国民の企業に対する信頼度は大きく低下するとともに、我が国の国際的な信用も損なわれる事態となっています。これは、これまで日本企業が経験したことのない深刻なものであり、今、改めて企業における倫理が問われています。
※ 経団連「経団連企業行動憲章 実行の手引き」より引用
このように、経済界を挙げて反社との一切の関係遮断への姿勢を示し、企業倫理の確立や遵法精神の徹底、健全な企業活動発展への心構えを宣言しています。
さまざまな反社チェックの手法
反社会的勢力と関わりを持たないように、自社で経営者や管理職、担当部門が行う反社チェックにはさまざまな方法が存在します。インターネット上で情報を検索する簡易的なものから、専門機関へ調査を依頼するものなど、手法によってかかる手間やコストも異なります。近年はIT技術の発展により、従来よりも手軽に反社チェックを実施できるツールも登場しています。
・インターネット検索
Googleなどの検索エンジンで、取引先名や名前を入力して調査。
・新聞記事データベースの検策
過去に報道された新聞記事のデータベースを参照し、取引先名や名前と関連する事件性のある記事がないかを調査。
・専門機関が独自に蓄積したデータベースの検索
専門調査機関が、独自のノウハウで蓄積したデータベースを参照してチェック。
・調査会社・専門家による調査
各種データベースの検索だけでなく、登記情報や現地調査など、広範囲にわたる調査を実施。
担当者が課題に感じる、情報源の信頼性
各企業が上に述べたような方法で反社チェックを行っていますが、Sansan株式会社が実施した調査によると、コンプライアンスチェックの担当者が抱える課題で最も多いのが「信頼できる情報源がどれだか分からない」というものでした。
Sansanでは、信頼できる情報減を参照し、担当者の手間がかかる反社チェックを自動化できるオプションサービスを提供しています。以下の資料で詳しく紹介しています。

リスクチェック powered by LSEG/KYCC
リスクチェックのサービスについて、ご利用の流れや導入後のメリットについて説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部