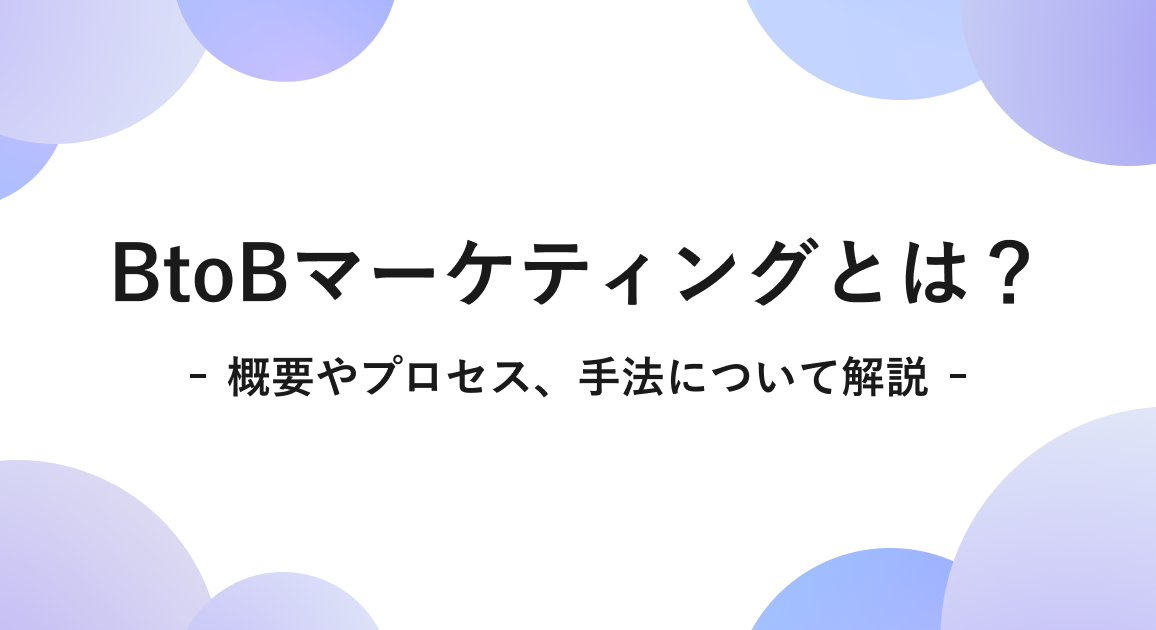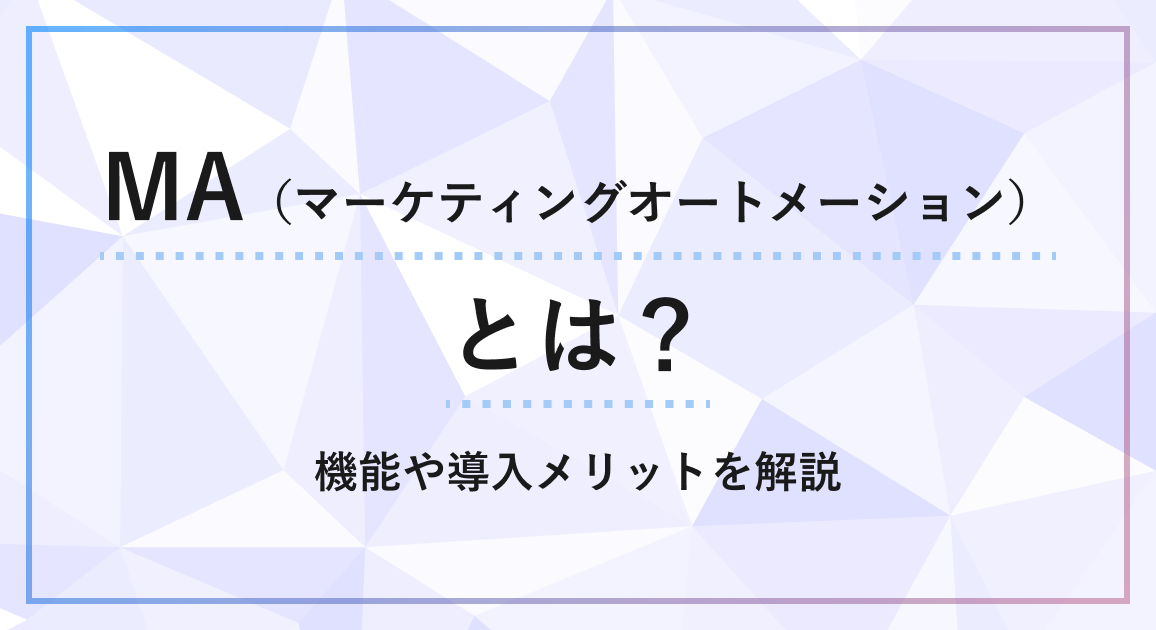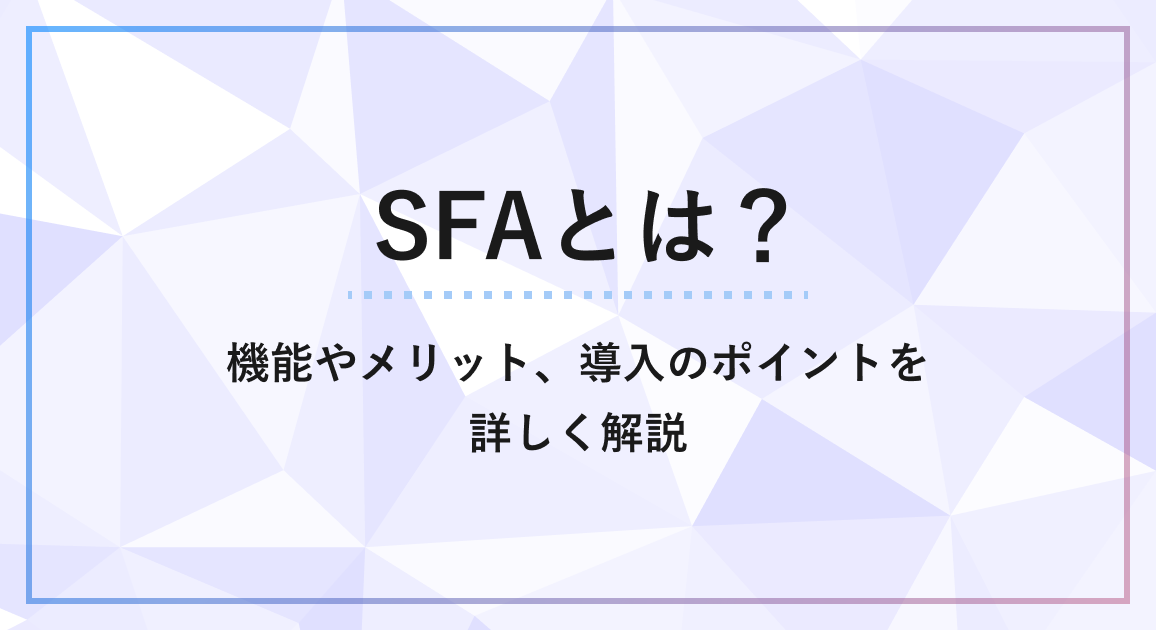- マーケティングノウハウ
ウェビナーが生産性向上に貢献、マーケティングに活用する方法とは?
公開日:
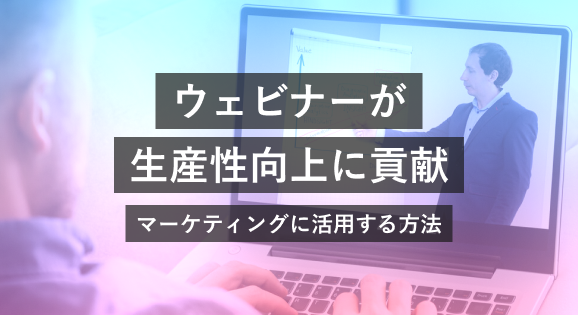
リード獲得やナーチャリング施策の一環として「ウェビナー」の開催が増えています。しかし、ウェビナーの開催ノウハウが分からず、右往左往している企業が多いのが実情ではないでしょうか。この記事ではウェビナーを開催するために必要な準備、生産性に貢献する理由を解説していきます。
※本記事は2022年10月に作成されました。掲載されている内容は作成時点の情報です。
目次
BtoBマーケティングに必要なウェビナー
ウェビナー(Webinar)とは、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合わせた造語で、「ウェブセミナー」や「オンラインセミナー」とも呼ばれています。 また、インターネットを介して行われるセミナーそのもの、もしくはウェビナーを実施するためのツールを指すこともあります。昨今の社会的情勢から、これまでオフラインで行っていたセミナーやイベントを、オンラインで行うウェビナーに切り替える企業は大変多いです。

データ分析を行う株式会社サイカの調査、「企業の広告宣伝担当者201人に聞いたテレワーク環境下でのセミナー開催に対する意識調査」によると、2020年の緊急事態宣言後にオフラインのセミナーを中止、あるいはオンラインに切り替えた企業は98.9%でした。そのうち「全セミナーをオンラインで開催した」のが36.8%、「一部のセミナーをオンラインで開催した」のが30.8%と、大多数の企業がオンラインセミナーを開催していたことがわかりました。
ユーザー数も順調に増えていることから、今後も継続あるいは加速すると予測されているウェビナー。ここで、ウェビナーが生むユーザー側へのメリットと、企業側へのメリットを紹介する。ユーザーと企業の双方で、以下複数のメリットがあることが判明しています。
ユーザーメリット
- 移動中や昼休みなど、場所や時間を問わず視聴できる
- オフラインよりも参加へのハードルが低い
- アーカイブ視聴で、セミナー後に繰り返し何度も視聴できる
- 通信環境さえあれば、国内外問わずどこからでも参加できる
- コメント機能を利用すれば、好きなタイミングで質問が可能
企業側のメリット
- 事前収録やリアルタイム配信など、状況や都合に合わせて形式を選択できる
- 会場費・人件費・移動費などの費用が不要
- 自宅からでも配信可能で、感染予防にも寄与する
- 資料配布もオンラインのため、印刷費も節約できる
- 録画をすれば、新人研修の資料や動画共有サービスへの投稿、次回セミナーへの活用などの二次利用が可能
- これまで参加不可だったユーザーも参加できるため、新たな人材の獲得ひいては海外や遠方へのビジネスチャンスにつながる可能性も
- 視聴後のアンケートをウェビナーのツール上で行うと、回答しやすく集計も簡単
ここまで、ウェビナーを開催することのメリットを紹介してきましたが、ウェビナーにはデリットもあります。
参加者とのコミュニケーションが取りにくい
参加者側はカメラ・音声をオフにしていることが多く、他の参加者のことも考慮すると発言がしづらい場合があります。チャットでやりとりできても、テキストベースとなるため配慮が必要です。
参加者の雰囲気を感じ取りにくい
真剣に参加している人がほとんどであったとしても、ウェビナーで個々の雰囲気を感じ取ることは難しい場合があります。オンラインでセミナーを開けるというメリットの裏には、こうしたデメリットがあることもきちんと認識しておくべきです。
新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず導入した企業も多いウェビナーですが、パートナーへの製品説明会や採用説明会、社内の勉強会など、マーケティング施策以外でもさまざまなイベント・セミナーに活用できます。ウェビナーの開催ノウハウを蓄積しておくことは、これからの企業経営やBtoBマーケティング活動において必須です。
ウェビナー開催への3つのステップ

ウェビナーは、製品説明会や採用説明会・社内の勉強会やミーティングなど、施策以外のさまざまなセミナーやイベントに活用できます。ここからは、ウェビナー開催に必要となるステップを説明します。ウェビナー開催へのステップは、大きく分けて以下の3つです。
- 目的を明確にする
- 通信環境を整える
- 集客を行う
それぞれのステップでのポイントを解説します。
1.目的を明確にする
まずはセミナーやイベント開催の目的に応じたテーマを検討します。例えばイベント開催の目的がリードナーチャリングなら、自社製品の活用術、導入事例の紹介などを行うのが適切です。また、自社製品に興味をもってもらうことが目的であれば、ユーザーが興味のあるテーマや、現在抱えている課題に対して、自社の商品を訴求することを考えたシナリオにします。
次に、開催日の選定です。視聴者を多く集めるには、視聴しやすい曜日・時間に開催したい。BtoBのウェビナーは、内容により勤務時間に視聴する人も多いため、平日昼間の開催が一般的です。
2.通信環境を整える
配信トラブルが発生しないよう、配信状況や機材について事前の確認作業を行います。自宅からの配信でも有線にする・映像や音声の鮮明化にカメラやマイクを用意する・講師が映る位置は適切かといったリハーサルを行うようにしましょう。また、配信内容の検討も必要です。資料を作成し、スライドが多くなる場合にはパソコンでの視聴を呼びかけるようにします。この他、チャットでの質問の受付や投票機能などを備えることにより、視聴者を飽きさせない工夫を行えます。配信ツール次第では、再生時間やアンケートの結果など、参加者ごとに視聴データを取得できます。
3.集客を行う
ウェビナーの集客は、メールや自社のWebサイトなどで集客を行います。ターゲットとなるリストを定め、イベント開催のメールを配信します。MAツールで配信するのであれば、HTMLでタグを埋め込み、開封数やアクセス履歴も分析しながら、サービスへの興味関心度合いを図りましょう。BtoBであればメールはシンプルなテキストメールでもよい。画像を使ったHTMLメールにするならば、自社サイトとデザインを合わせると違和感がありません。
自社サイトも告知を載せ、URLをメールやSNSなどで拡散します。掲載する項目は、テーマ、日時、参加方法などはもちろんのこと、イメージ画像やアジェンダ、講師の紹介、参加するメリットも盛り込みましょう。サイトに掲載する申し込みフォームは、参加申込時に離脱が発生しないように、簡潔かつ、分かりやすい流れで登録できるフォームにできるとよいでしょう。
アフターフォローも忘れずに

ウェビナーの終了後は、参加のお礼メールとアンケートの送信を心がけましょう。アンケートではコンテンツの内容や、運営についてイベントの満足度を調査します。
回答したユーザーにはお役立ち資料の配布など特典があると回答率が上がりやすく、さらに動画の視聴データとMAやSFAなどとデータ連携を行えば、参加者の興味度合いを図る材料として活用することができます。
効率のよいウェビナー開催が生産性向上につながる
オフラインのセミナー開催でかかっていた時間や移動、コストが削減されることにより、その分、従業員は本来やるべき業務に集中することができます。自分が注力すべきことに取り組める環境は、ストレスなく働きやすいといえるでしょう。業務がスピーディーに進んだり、課題解決やPDCAサイクル早くまわせたりといった生産性向上につながります。
生産性向上は業務効率化と混同されがちですが、生産性向上のための施策の一つが、業務効率化だといえます。
ウェビナーは現代に必須のマーケティングツール
ウェビナー開催時には考えるべきポイントが多く、どこから手をつけたらよいか頭を抱えてしまう担当者が多いでしょう。ですが、ウェビナーの需要は今後も継続あるいは加速すると予測されています。未導入の企業は、導入をぜひご検討ください。

部門別Sansan活用例〜マーケティング部門編〜
Sansanを全社でご利用いただくと、マーケティング部門でどんなメリットを感じるか、具体的にイメージしやすくなる資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部