- 営業ノウハウ
オンライン商談ツールのメリットやデメリットは?導入手順や活用のポイントを解説
公開日:
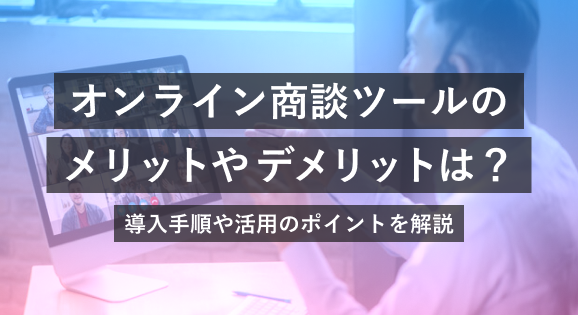
※本記事は2020年4月に作成されました。掲載されている内容は作成時点の情報です。
2020年4月、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発令された緊急事態宣言によって、企業の営業活動は大きな影響を受けました。これにより、多くの企業でテレワーク(リモートワーク)が導入され、オンラインでの営業活動が主流となりました。本記事では、多くの企業が実施しているオンライン商談のメリットとデメリットから、オンライン商談の効率を上げる代表的なツールまでを紹介します。
目次
オンライン商談とは
オンライン商談とはITツールを活用してオンライン上で商談を行う営業手法です。従来の商談は客先を訪問し、対面での実施が一般的でした。しかし新型コロナウイルス感染症の拡大に伴ってオンライン商談が大きく注目され、現在では大企業だけでなく中小企業もオンライン商談を導入するようになってきています。
対面商談やウェブ会議との違い
オンライン商談と対面商談の大きな違いは、コストや時間が少なくてすむ点です。対面商談であれば客先を訪問するための交通費もかかるし移動時間もかかります。しかし、オンライン商談であれば、相手と時間を決めるだけで良いので交通費はかかりません。さらに、オンライン商談に使われるITツールは交通費よりもずっと安価である場合が多いです。
オンライン商談とウェブ会議との違いの一つは専用アプリケーションが必要かどうかです。ウェブ会議は専用のアプリケーションをインストールし、お互いがアプリからアカウントにログインしてないと利用できない場合が多くあります。しかし、オンライン商談はブラウザ上で動き、専用アプリケーションもログインもいりません。顧客との商談に専用アプリケーションの導入をお願いするのは相手の負担にもなるためハードルが高いが、オンライン商談であればURLや接続番号を伝えるだけで手軽に利用できるのです。
また、想定される参加人数も違いの一つです。ウェブ会議システムは数十人から数百人規模の会議も想定されますが、オンライン商談は1対1か、多くても数人が想定されます。
オンライン商談のメリットとデメリット

オンライン商談のメリット
オンライン商談では、従来の訪問・対面での営業スタイルに比べて効率的に営業活動を行うことが可能です。具体的なメリットは、以下が挙げられます。
メリット1:移動時間とコストを削減
メリット2:遠方の顧客への営業アプローチが容易になる
メリット3:リードタイムを短縮
メリット4:ペーパーレス化を促進
メリット5:アポイントが取りやすくなる
メリット1:移動時間とコストの削減
オンライン商談は、顧客の元へ訪問する必要がないため、これまで移動にあてていた時間を商談の事前準備や顧客フォロー、他の優先すべき業務に振り分けられます。また、1日当たりの商談数を増やすことも可能となり、成約数・売り上げの底上げも期待できます。さらに、移動にかかる交通費や残業代、資料の印刷代など、大幅なコスト削減にもつながります。
メリット2:ビジネスチャンスの拡大
訪問営業の場合、近場の限られたエリアでしか営業活動ができないことも多いです。全国的に営業活動を展開しようとすれば支社・出張所の開設や出張が必要となり、コストの負担も大きくなってしまいます。オンライン商談であれば、営業エリアに制限は無く、日本各地、さらには、海外の顧客にもアプローチできるため、ビジネスチャンスが拡がります。
なかなか訪問ができず、これまで機会を逸していた新規顧客開拓や顧客フォローも実現できるでしょう。
メリット3:リードタイムの短縮
オンライン商談の場合、参加者の人数に際限がないため一度に大人数と商談を行えます。決裁者や他の部署のメンバーが気軽に参加できるので会議の回数を重ねる必要もなくなり、リードタイムが大幅に短縮できます。
メリット4:ペーパーレス化の促進
オンライン商談はインターネット上で行われるため紙の資料は必要なく、電子データをクライアントと共有するだけで済みます。したがって、印刷費の削減、印刷作業の工数削減が期待できます。また、クライアントへの訪問途中の資料紛失など情報の漏えいも防げます。近年のオンライン商談ツールは強靱な情報セキュリティー対策が施されており、紙媒体を携帯するよりも漏えいの可能性は低いと考えられます。
メリット5:アポイントが取りやすくなる
実際に訪問して営業するとなると、売り込みの姿勢に圧迫感を覚えるクライアントもいます。たとえ気になる商品であっても、その場で営業担当者のペースで購入を迫られることに不安を感じてしまいます。それゆえクライアントから警戒され、なかなか商談につなげられません。しかし、オンライン上のやり取りであれば心理的ハードルは低く、オンライン商談は対面商談よりもアポイントを取りやすいと言えます。
オンライン商談のデメリット
一方で、オンライン商談にもデメリットはあります。そこに対しては、事前に対策を取っておきましょう。
デメリット1:事前準備や相手に合わせた柔軟な対応が必要
デメリット2:インターネット環境に左右される
デメリット3:手軽にできるためキャンセルされるケースも多い
デメリット4:信頼関係が形成しにくい
デメリット1:事前準備や相手に合わせた柔軟な対応が必要
使用するオンライン商談アプリやツールによっては、商談相手に事前登録やインストールをしてもらう必要があります。商談相手が対応可能なオンライン商談の環境や、デジタルリテラシーに応じて、丁寧な説明や事前準備など柔軟に対応することが不可欠です。
デメリット2:インターネット環境に左右される
商談中、インターネット接続環境が不安定だと、映像や音声が途切れて、商談相手とのコミュニケーションが取りづらくなります。商談時は、相互のインターネット接続環境を確認し、安定した状態で商談できるように留意しましょう。場合によっては、代替の連絡手段として携帯電話を用意し、いざという時の対応ができるようにしておくと良いでしょう。
デメリット3:手軽に開催できるためキャンセルされるケースも多い
オンラインの手軽さから、気軽にキャンセルしやすいという心理的傾向があります。商談のアポイントは、なるべく近い日程で設定し、前日に相手へリマインドの連絡をしておきましょう。
デメリット4:信頼関係が形成しにくい
オンライン商談は対面商談よりも信頼関係の形成がしにくい面があります。オンラインだと対面よりも相手との距離感が生まれるともに、コミュニケーションが簡素になりがちです。商談に必要な情報なやり取りのみ交わされたり双方の表情や温度感が伝わりづらかったりします。お互いに打ち解けられないまま営業担当者から一方的に会話が進められれば、クライアントは冷静な思考になってしまいます。
クライアントにも質問を投げかけて話してもらうように意識するなど、熱量の不足を補わなければ成約率が下がってしまう可能性があります。
オンライン商談ツールの導入手順

オンライン商談も対面商談も商談の流れ自体は変わりません。対面商談では客先を訪問していた部分をオンライン上に変えるだけです。しかし、インターネットを利用するのでそれなりの準備と整備は必要になります。
手順1:インターネット環境の整備
オンライン商談において最も気をつけるべきはインターネット接続の安定性です。せっかく商談が佳境に入っていたのに接続が途切れてしまうと、顧客に不快感を与えてしまい、水の泡になりかねません。オンライン商談を行う際にはテザリングなどの不安定な環境よりは大容量の固定回線など安定した接続環境で行うことが望ましいです。
手順2:営業資料とシナリオの用意
インターネット環境が整ったら、営業資料とシナリオを用意します。このとき、対面商談よりも細かい意思を言葉ではっきり伝えるようにシナリオを作ります。オンライン商談では、対面商談のようなその場の空気感による“阿吽の呼吸”は通用しないと思っておいたほうがいいです。例えば相手に資料を出す場合にも、対面の場合は待っていれば資料が出てくるとわかりますが、オンラインだとわかりにくいです。したがって「資料を用意しますので少しお待ちくださいね」など今からやる動作や意思を言葉で伝えたほうが良いです。
手順3:ツールの選定とテスト
営業資料とシナリオが用意できたらツールの選定をします。オンライン商談のツールにはさまざまあり、そなわっている機能が違うので自社とクライアントの商談に必要なツールを選びます。ツールが決まったら必ず事前にカメラと音声のテストを行います。
手順4:商談
表情や身振り手振りは画面越しだと伝わりづらいです。よってオンライン商談中は対面商談のときよりも、ややオーバーリアクションが良いです。また、理解できているかどうかの確認も対面の場合より増やすと良いでしょう。
手順5:アフターフォロー
オンライン商談が注目されてまだ2年程度しか経ってないので、 相手もオンラインには慣れていない場合が想定されます。よって、商談後のお礼のメールは欠かさないようにしましょう。できれば当日中に送るべきです。その際、商談中にわかりにくかった点は無かったか、質問を促すと良いでしょう。
オンライン商談ツール活用のポイント
ポイント1:事前テストは入念に行うこと
先述したように商談に入る前にカメラとマイクのテストが必要になるが、これはただ映るレベルではなく、相手に不快感を与えないかどうかもチェックするべきです。
例えば、カメラ位置が高すぎたり低すぎたりすると目線の高さに違和感が出て印象が悪くなります。自分の目線よりも少し高い程度の位置に来るように調整するとよいでしょう。特にノートPCのカメラを使う際は上から見下ろすような視線になってしまいがちなので注意すべきです。
また、マイクの感度も重要です。マイクの感度が低いと声が小さすぎて聞こえず、感度が高すぎると音割れして耳障りです。オンライン商談ツールにはマイクやカメラのテスト機能が付いているツールもあるので、このような機能を上手く活用するべきです。
ポイント2:リマインドメールを送ること
オンライン商談も対面商談も重要度に差はないのだが、オンライン商談のほうが軽く見られやすい傾向があります。よって、商談の予定を相手に忘れさせないよう、リマインドメールを送ったほうがよいです。オンライン商談は気軽にできる反面、熱が冷めやすいのがデメリットです。アポイントを取ったときは相手が乗り気でも、すぐに熱量が下がってしまいます。リマインドメールを送信し、対面と変わらないれっきとした商談なのだと相手に認識してもらうのが重要です。
ポイント3:リードタイムは短く取ること
オンライン商談は熱量が下がりやすいので、リードタイムは短く取るべきです。当日、翌日、翌々日ぐらいまでが望ましいです。商談後に顧客から問い合わせがあった場合にもできるだけ即日に返信するべきです。オンライン商談は熱量を維持するために対面商談よりもスピーディーに事を運ぶのがコツです。
オンライン商談で営業力の向上を実現
今後、ビジネスシーンでは、対面営業での良さは生かしつつも、オンライン化がますます進み、オンラインでの商談は増えていくと予想されます。本記事で紹介したオンライン商談のメリット・デメリットを押さえ、営業活動の業務効率化を図ることで、営業力の向上にもつなげましょう。
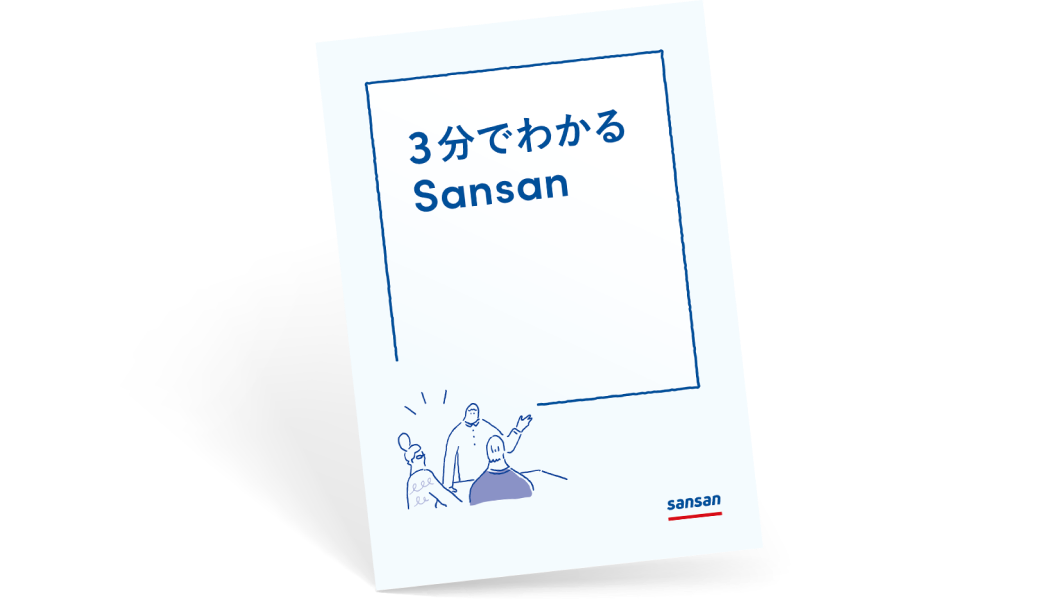
3分でわかる Sansan
営業DXサービス「Sansan」について簡潔にご説明した資料です。

ライター
営業DX Handbook 編集部